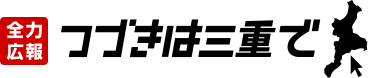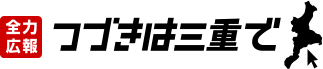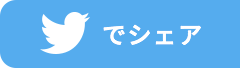【取材】yusuke.murayama
突然ですが皆さま、このお洒落な蝶ネクタイは何からできているかご存知だろうか。
実はこれ、三重県尾鷲市の漁師たちが使っていた大漁旗からできている、「尾鷲大漁旗リメイク雑貨FLYKI」(以下、「FLYKI」)という商品。都市部の百貨店でも、期間限定で販売された。
以前は大漁旗職人が多数いた尾鷲市だが、今ではたった一人になってしまった。
「尾鷲の大漁旗文化をなんとか形にして残したい」そんな想いから作りはじめたのものだ。
取り組んでいるのは、尾鷲市のNPO法人、天満浦百人会(以下百人会)。
(百人会という名前だが、実際は20人ほど。「多くの皆さんの協力によってまちづくりをしたい」という願いを込めて付けられた名前とのこと)
天満浦には、昔から自らが暮らす “まちをつくる” といった活動が根付いており、生活協同組合のような仕組みもあったという。

「FLYKI」の作者である、タナカカツマサさん。タナカさんは津市でデザイナーとして暮らしているが、百人会のメンバーでもある。
タナカさんが手がけた商品は、FLYKIだけでなく、百人会のロゴや広報媒体(ホームページやチラシ)の制作、イベントなどにも企画段階から参加している。
今回、タナカさんに同行していただき、尾鷲市天満浦の天満荘で百人会を取材した。

尾鷲市の代表的な産業である漁業。港や漁船を一望できる場所に天満荘はある。



———移住者が “まちをつくった” 天満浦。

大漁旗から作ったお洒落なエプロンを着た、百人会のメンバーにお出迎えいただいた。
取材にあたって、いろいろと天満浦のことを調べた際、最も気になったことが、天満浦には移住者が多いということ。そこで、 移住者とまちづくりの関係。その辺りを百人会代表の松井さんに伺った。


天満浦には最近も移住してきた方がいたり、大阪や東京といった都市部から若者が短期間で居住することもあるという。
現在、200人ほどが暮らしているが、天満浦で生まれ育ったという人は現在4人ほど。子どもの数も約12人と少ない。
市外・県外からの移住者が多いのだ。
その中で、まちづくりを中心的に行ってきたのが、松井さんたち“おかあちゃん集団” なのだ。

どのような経緯で松井さんたちはまちづくりを行ってきたのだろうか。
松井さんは「民生委員によって、まちは大きく変わる」という。松井さんは、「安心・安全して暮らせるまちにしたい」との想いから、民生委員をしていた。
松井さんが嫁いできた当初、まちは今ほど開放的な雰囲気はなかった。
まちに暮らす方々がもっと仲良くなれば、安心・安全して暮らせるまちになると考え、そのためには開放的なまちにする必要性を感じたという。
そして1959(昭和34)年に、青少年育成町民会議をまちのおかあちゃんを中心に立ち上げた。
1970年代のオイルショック時には、「小さな子どもを抱えて、たくさんの生活品や食べ物を買いに行けない」状況だった。そのため、独自で生活協同組合のようなシステムを構築した。学生服や運動服は大阪から、洗剤は四日市から、ハムは熊野からなど、生活に必要なものを各地から集めた。
そのような仕組みを作って以降。毎月1回の会合を行ったり、年に1回、活動をまとめた会報誌を発行したりするようになった。

青少年育成町民会議は、発足時に30年経ったらやめる方針だったが、今でも続いている。それが現在の百人会だ。みんなが集まって、いろいろと楽しむためのコミュニティとしても残っているため、30年で組織を解散しなかったとのことだ。


———外部のクリエイターや若者がまちづくりに与える影響とは!?
商品開発以外にも地元の商工会議所や外部クリエイターなどと連携しながら活動している。
これは、尾鷲商工会議所が、地場産業である水産業の振興を目的に、大漁旗にスポットを当てた映像を制作したもの。制作は、国内外で活躍する映像作家である菱川勢一氏率いるドローイングアンドマニュアル株式会社だ。
このように、外部の視点を取り入れることで、非常に斬新でスタイリッシュな作品になる。



さらに、百人会のメンバーにデザイナーのタナカさんが加わったことで、イベント自体の魅力を引き出し、訴求効果を上げている。そして、それらの企画・デザインなどをホームページやSNSなどを通して効果的に情報発信することで、若者が集まっているという。
![TENMA-FUYU-A3[1]](https://www.mie30.pref.mie.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2017/02/TENMA-FUYU-A31-212x300.jpg)
「若者が天満浦に集まることで、百人会の方々は若者の視点を知ることができ、次のイベント企画の参考にしている」と松井さんは嬉しそうに語った。
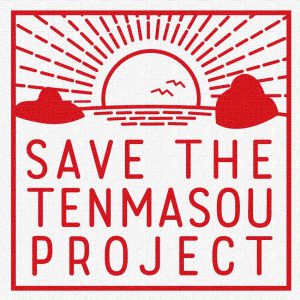
地元のおかあちゃん × クリエイターやデザイナー × 外部の若者。
彼らが創り出す良い循環が、日光が燦々と降り注ぐ天満浦を、さらに明るくしている。
———損得勘定ではなく “まちをつくる” という楽しみ。
まちづくりというと、難しくて何か特別の専門知識が必要だと思いがちだ。
でも百人会の皆さんのように、まちづくりを楽しみ、そして支え合いながら続けることで、まちは変わっていくのだと実感した。
最後に、これからの世代がまちづくりをする際に大切なことは何か、松井さんに伺ったところ、次のように仰った。
- スマホやパソコンで繋がるのもいいが、実際に会って話すことが大切
- 損得勘定ではなく、まちをつくる、そして変わっていく。このこと自体に喜びを感じなければ
- リーダーはまず、自分が泥にまみれながら、身を粉にする。そうでなければ人は感動しないしついてこない
- 今の時代、自分から何か人が少ない。責任を負いたくないからだと思うが、リーダーは全責任を負う覚悟が必要

今回、強く感じたことがある。
自分が暮らすまちは、そこに当たり前のように存在しているが “誰かがまちをつくっている” ”誰かがつくってきた歴史がある”
まちづくりというと行政の仕事と思いがちだが、今回の百人会のように、自らが暮らすまちをつくっている方々がいる。しかも楽しみながら、繋がりながら。
あなたの暮らすまちは、誰がつくっているのだろう。誰がつくってきたのだろう。
そして、これからの未来を担う子どもが暮らすまちは、誰がつくっていくべきなのだろうか。
若者や親世代だけなのだろうか。

「この歳までまちづくりをしているとね、もうね、苦労も楽しくなってくるんです」と松井さん。
きっと、まちづくりをした人しか見えない、イキイキとした世界があるはずだ。
尾鷲の食文化を若い世代へ継承する取り組みがスタートしていると聞いた。
まちづくりに年齢は関係なさそうだ。むしろ、いろんな世代が繋がることで魅力的なまちに変わっていく。

大切なのはそう、できるだけ楽しく!
【取材協力】
NPO法人天満浦百人会
住所:三重県尾鷲市天満浦161番地
TEL & FAX : 0597-22-7880
ホームページ:http://tenmaura.org
Facebook:https://www.facebook.com/tenmaura/
関連情報